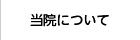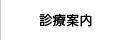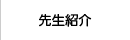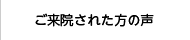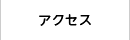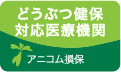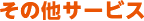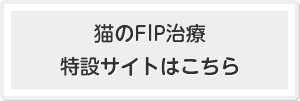最近のエントリー
月別 アーカイブ
- 2026年1月 (1)
- 2025年10月 (1)
- 2025年7月 (1)
- 2025年5月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年10月 (3)
- 2024年9月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (4)
- 2024年3月 (8)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (7)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (6)
- 2023年10月 (7)
- 2023年9月 (7)
- 2023年8月 (5)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (1)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (2)
- 2022年9月 (3)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (3)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (2)
- 2022年4月 (1)
- 2022年3月 (1)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (3)
- 2021年9月 (3)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (3)
- 2021年6月 (5)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (5)
- 2021年2月 (3)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (5)
- 2020年11月 (1)
- 2020年9月 (1)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (2)
- 2020年1月 (2)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (3)
- 2019年9月 (4)
- 2019年8月 (2)
- 2019年7月 (5)
- 2019年6月 (6)
- 2019年5月 (6)
- 2019年4月 (4)
- 2019年3月 (5)
- 2019年2月 (6)
- 2019年1月 (3)
- 2018年12月 (5)
- 2018年11月 (6)
- 2018年10月 (6)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (2)
- 2018年4月 (2)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (3)
- 2017年12月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年5月 (1)
- 2017年3月 (1)
- 2017年2月 (2)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (2)
- 2016年10月 (1)
- 2016年9月 (1)
- 2016年7月 (1)
- 2016年6月 (2)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (2)
- 2016年3月 (2)
- 2016年2月 (2)
- 2016年1月 (2)
- 2015年12月 (1)
- 2015年11月 (2)
- 2015年10月 (1)
ブログ 5ページ目
Merry Christmas!!

この年は多くの出来事と挑戦を経験した方も多いかと思います。
またワンちゃん、猫ちゃん、ご家族で過ごす機会が多い時期でもあります。


この機会に今年を振り返って1年の感謝を伝えたり、皆さんで素敵な年末をお過ごしください。

https://www.dropbox.com/scl/fi/lkbhtz7ofxfbe4mqjflr2/2312.pdf?rlkey=02ef2l47uggbeh9ebsydslfte&dl=0
(ココニイル動物病院)
2023年11月28日 15:27





犬の行動から感情を知ろう 楽しい・嬉しい編
 どんな時に嬉しい?
どんな時に嬉しい?
・飼主さんから褒めてもらったとき
・大好きなご飯やおやつを貰ったとき
・飼主さんと一緒にいるとき
・撫でてもらっているとき
 どんな時に楽しい?
どんな時に楽しい?
・一緒にお散歩やお出かけのとき
・遊んでもらっているとき
・探索をしているとき
・犬好きの子がほかの子と遊んでいるとき
尻尾をブンブン

・一番わかりやすい表現です
・尻尾と一緒に腰まで動いちゃう子や
ピョンピョン跳ねる子もいます
・怒っているときや警戒しているときも尻尾を振ることがあります
併せて表情も確認してみましょう
甲高い声で鳴く

・言葉が話せないワンちゃんたちは喜びを伝えようとおしゃべりをしてくれます
・「キャンキャン」や「ワォンワォン」と短く鳴きます
口角が上がり目を細める


・人の表情をよく見るワンちゃんたちは真似をしている
という説があります
・にっこり笑っているような表情は人にも伝わりやすいです
・緊張している時や暑い時のパンティング(ハァハァする様子)
の際は目が開いていることが多いです
状況から考える

・動物の行動は分からないことが多いです
・感情の表現には個体差があります
・紹介したは一例です
・シチュエーションから動物の感情を読み取ってあげることも大切です
・先程のことも気にしつつよく観察してみましょう
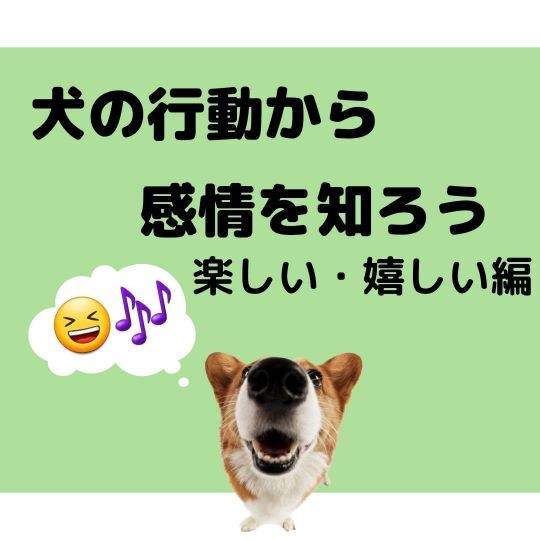
(ココニイル動物病院)
2023年11月21日 14:56





犬の歴史について

近年、犬の祖先はオオカミであることが分かりました。

具体的な進化は歴史が古くはっきりしていませんが品種改良のために同じイヌ科の
「ジャッカル」や「コヨーテ」などと交雑した可能性があると言われています。
オオカミから犬へ

野生のオオカミは食べ物を確保するため狩猟が必要でした。
しかし、人間の残り物を食料として得られることを学び、人間の集落に住み着くようになりました。
今では、オオカミは人間や家畜を襲う動物として怖がられていますが、このころは人間もオオカミを狩猟のパートナーとして受け入れていたようです。
野犬から家族へ

人間が犬と暮らすようになったのは、約1万5000年前頃と言われています。
獲物を捕まえる狩猟文明から、作物を育てて収穫する農耕文明へと
人間の生活が変化したことで犬との関係も変化しました。
現在は人間を助けるために様々なところで活躍しています。
人間を助ける犬の仕事

例えば・・・
補助犬として 盲導犬・聴導犬・介助犬など
警察犬として 足跡追及犬・臭気選別犬など ほかにもさまざまな仕事をしています



(ココニイル動物病院)
2023年11月13日 15:39





フードの保管方法
 ドライフードの保管方法
ドライフードの保管方法
・直射日光を避ける
温度上昇は劣化が早くなる為、直射日光が当たる場所での
保管は避けましょう。
・高温多湿を避ける
高温多湿状態になるとカビが発生し、
それを餌とする害虫も発生する為避けましょう。
・密閉状態にする
空気に触れることで酸化が進んでしまう為、
空気を抜き密閉して保管しましょう。
※商品によって保管方法が異なる場合があります。
 セミドライフード(半生フード)の保管方法
セミドライフード(半生フード)の保管方法
・基本、開封したその日に食べきる
ドライフードに比べてセミドライフードは、水分量が多く
腐りやすい為、開封日に食べきるのが基本です。
もし食べきれない場合は、密閉して冷蔵保管しましょう。
※商品によって保管方法が異なる場合があります。
 ウェットフードの保管方法
ウェットフードの保管方法
・冷蔵保管をする
水分量の多いフードはすぐに傷みやすい為、
開封後は密閉して冷蔵保管しましょう。
冷蔵保管でも2日以内に使い切り、冷蔵後は人肌くらいに温めてからあげましょう。
※商品によって保管方法が異なる場合があります。
 まとめ
まとめ
水分や脂肪が多く含まれているフードは酸化しやすく
味・臭いの変化や、わんちゃん・ねこちゃんの健康にまで
影響を与える心配があります。
健康を長く守るためにも保管方法には注意が必要です。

(ココニイル動物病院)
2023年11月 4日 15:19





異物摘出を内視鏡で行った犬
(ココニイル動物病院)
2023年11月 1日 18:05





避妊・去勢の大切さ
多くのわんちゃん・ねこちゃんが最初に経験をする手術だと思います。

家族にお迎えしようと考えている方
避妊・去勢を考えている方
これから紹介するメリット・デメリットを考慮して、
決断して頂ければ幸いです。

 メリット
メリット
・望まぬ妊娠を避けることが出来る。
・性ホルモンが原因の病気を予防できる。
・マーキングなどの問題行動をある程度抑制できる。
・発情に関するストレスを無くすことが出来る。
 性ホルモンの病気
性ホルモンの病気
 男の子・・・前立腺肥大、肛門周囲線種
男の子・・・前立腺肥大、肛門周囲線種会陰ヘルニア、精巣腫瘍(がん)等…
 女の子・・・子宮蓄膿症、乳腺腫瘍
女の子・・・子宮蓄膿症、乳腺腫瘍卵巣・子宮腫瘍(がん)等…
上記の病気は手術である程度のものは予防が出来ますが
放っておくと命に関わるものもあります。

避妊・去勢の手術時期は最初の発情期を迎える前の
生後6か月ごろが適切とされています。
 デメリット
デメリット
・全身麻酔によるリスク
健康な子の麻酔のリスクは0.01%程と言われています。
・肥満になりやすくなる
避妊・去勢をすると基礎代謝が落ち、太りやすくなります。
・尿漏れ
ごく稀に避妊後に尿漏れが起きることがあります。
・繁殖できなくなる
紹介したメリット・デメリットはあくまでも一部にすぎませんが、
これらを考慮したうえで決めて頂ければ幸いです。

「もう少し詳しく知りたい!」という方は御相談のみでも構いません。
動物病院へお越しください


(ココニイル動物病院)
2023年10月29日 15:09





2023年秋季セミナーに参加しました!
先日開催された、日本獣医エキゾチック動物学会主催の
秋季セミナーに参加いたしました

今回はエキゾチック動物の眼科についてのセミナーでした


エキゾチックアニマルの病気や治療は日々新しくなっており、
私たちもすべての動物たちに寄り添う医療が提供できるように
精進していきますので、皆様宜しくお願い致します


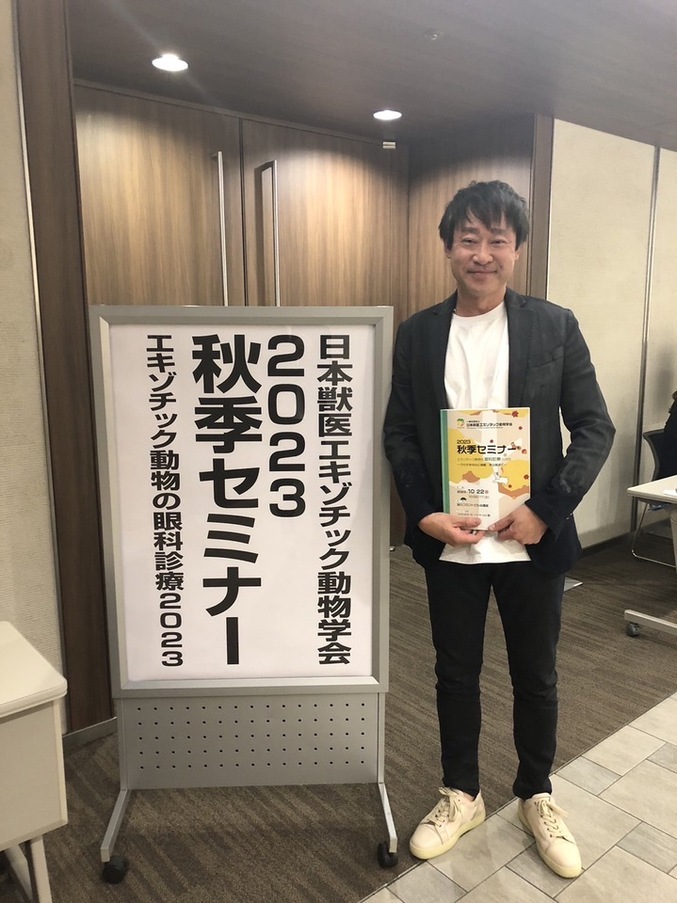
(ココニイル動物病院)
2023年10月25日 14:58





11月と言えば、七・五・三ですね!

皆様のお家にいるご家族同様のワンちゃん・ネコちゃんの健康にも気を配れていますか?

気温の変化などにより、ワンちゃん・ネコちゃんは、体調を崩しやすくなるため、冬の寒さにまけないように、しっかり備えていきましょう!!


https://www.dropbox.com/scl/fi/fnsymq8y1guapfhvxz3dr/2311-20.pdf?rlkey=87qn7kb3vsilzrzcbg2ljuzff&dl=0
(ココニイル動物病院)
2023年10月24日 14:56





犬の爪切りのやり方

・伸びていると爪が引っかかって怪我をしてしまいます。
・地面に当たって歩行しにくくなります。
➡その為、関節を痛める可能性があります。
爪切りの頻度は?

目安は月に1度

・その子よって伸びるスピードが違うので
1~2週に1度様子を見てあげましょう!
・わんちゃんが立った状態で爪の先端が地面につかないくらいが
理想的な長さといわれています。
 歩いた時にカチャカチャ鳴らないくらい
歩いた時にカチャカチャ鳴らないくらい
爪は白い?黒い?

【白い爪】
・ピンクに透けて見えるのが血管です。
・出血しないように血管の少し手前までを目安に切ります。
【黒い爪】
・血管が見えないため、少しずつ削っていくイメージで切ります。
・切り始めは爪の断面が固いです。
・爪の中心が柔らかくなってきたら血管が近いので止めます。
やってみよう!

・周りの毛を切ってしまわないように毛をかき分けて爪を出します。
・爪をしっかり握り、先端から少しずつ切ります。
・血管手前で止めます。
・爪やすりで角をとります。
出血してしまった

・止血剤をつける
・ガーゼやコットンで押える
・止血剤がない場合、小麦粉で代用する
まとめ
・爪切りは犬の健康を守ることにもつながります。
・上手にできたらご褒美をあげましょう。

・ご自宅での爪切りが難しいと感じたらお気軽にご相談ください


(ココニイル動物病院)
2023年10月23日 15:10





知ってほしいイエローリボンの意味について
 イエローリボンとは
イエローリボンとは
・健康上の理由があるわんちゃん
・トレーニング中のわんちゃん
・極度の怖がりなわんちゃん
・ほかのわんちゃんが苦手 など
様々な事情を抱えたわんちゃんが、お散歩中のリードや
ハーネスにつける大きくて目立つ黄色いリボンです

 イエローリボンの歴史
イエローリボンの歴史
2016年スウェーデンにて、様々な理由から人やわんちゃんとの交流が
難しい子たちへの理解を深めるために、わんちゃんの心理学者や
ドックトレーナーのグループがはじめたものです。
現在、欧米では活動が広がってきています。
しかし日本ではまだ認知度が低いようです。
 イエローリボンをしているわんちゃんと会ったら
イエローリボンをしているわんちゃんと会ったら
・距離をとってそっとしておきましょう
見知らぬ人やわんちゃんと交流するのが苦手な子もいます。
そんな子には距離を保つ事が最大の「思いやり」となります。
・目は見ないようにしましょう
緊張しているときや、怖がっている子に対して目を合わせてしまうとストレスを感じたり、
敵意を感じ攻撃行動をする場合があるので見つめないようにしましょう。
 イエローリボンをつけるときは?
イエローリボンをつけるときは?
イエローリボンをつけるのには注意も必要です。
トレーニングをしてあげることも飼主さんが出来るわんちゃんへの愛情です。
飼主さんの判断でイエローリボンをつけてしまうことで、そのわんちゃんの社会化のチャンスを
奪ってしまうことも…。
心配な方はドックトレーナーさんに相談してみましょう。
 わんちゃんも人もストレスなく過ごせるようにしていきましょう!
わんちゃんも人もストレスなく過ごせるようにしていきましょう!
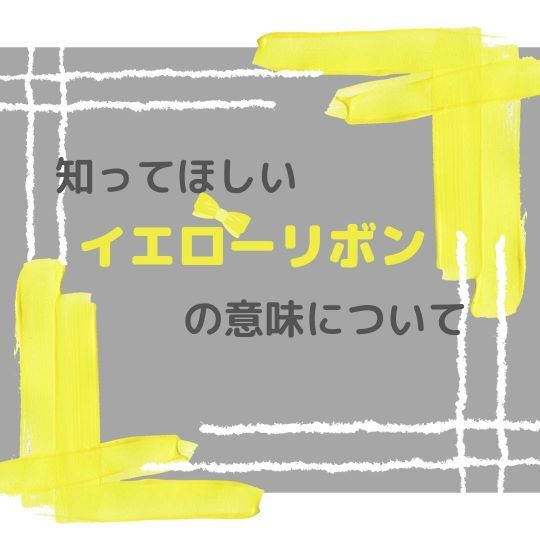
(ココニイル動物病院)
2023年10月15日 14:57





<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|次のページへ>>
100件以降の記事はアーカイブからご覧いただけます。